
持続可能な働き方の実現に向けたワークライフバランス推進の課題と解決策【RMFOCUS 第93号】
 RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます
RM NAVI会員(登録無料)のみ全文閲覧できます
[このレポートを書いた専門家]
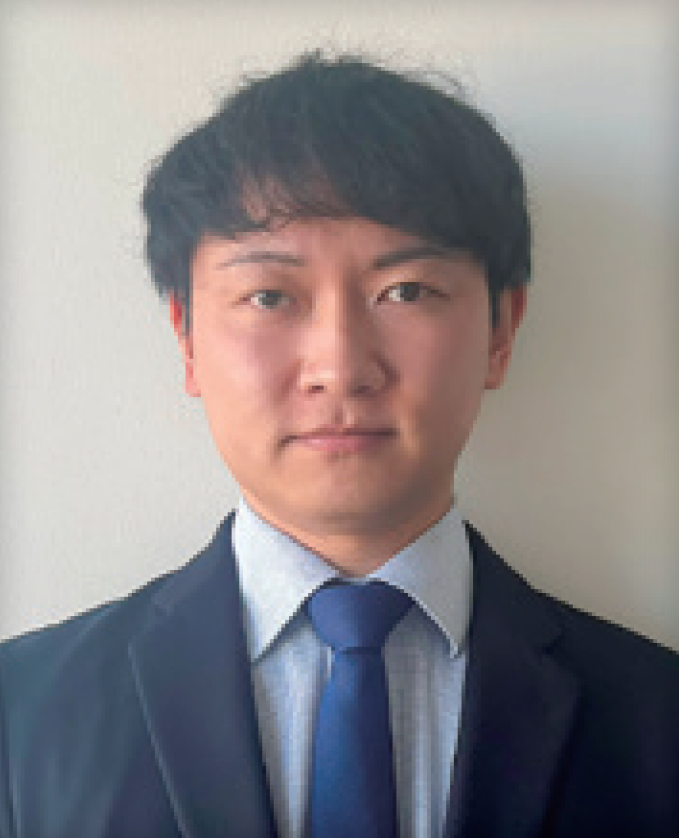
- 会社名
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 所属名
- リテールマーケット戦略部 地方創生推進チーム
2024年度自治体職員派遣研修生 - 執筆者名
- 特別推進役 齊藤 健志(秋田県研修生) Kenshi Saito
2025.4.2
- ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和を意味し、仕事の責任を果たしながら家庭や地域生活にも時間を割き、充実感を得られる状態。個人にとっては健康で豊かな生活を送るために、企業にとっては従業員の満足度や定着率を高め、生産性を向上させるため、社会全体では、少子化対策や健康寿命の延伸、社会的コストの削減に寄与するため、ワークライフバランスの実現が必要とされる。
- ワークライフバランス推進は人口減少による人手不足の中で、労働環境の改善に必要不可欠であり、一定程度の推進が見られる一方で、企業・管理職側はコストの増大や業務調整の難しさといった課題も存在し、まだ完全に普及しているとは言い切れない状況である。
- ワークライフバランスの推進には行政と企業の協力が不可欠であり、制度の拡充と従業員の理解促進を通じて、持続可能な働き方を実現することができる。
近年、ワークライフバランスの重要性がますます高まってきている。少子高齢化による労働力不足、従業員の多様化、価値観の変容などを背景に、仕事とプライベートの調和は、個人、企業、社会全体の持続的な発展にとって不可欠な要素となっている。本稿では、日本におけるワークライフバランス推進の現状と課題を、統計データや政策、企業の取り組みなどを交えながら考察する。
1. ワークライフバランスの定義と推進することによるメリット
ワークライフバランスは日本では1990年ごろから普及した考えで、2007年に内閣府が「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」 1)を策定したことで本格的に力を入れた取り組みが始まっている。このワークライフバランスの推進は、個人、企業、社会全体に多岐にわたるメリットをもたらす取り組みであるといえる。
個人にとってのワークライフバランスを推進することはまず心身の健康向上につながり、仕事とプライベートの調和がとれることで、ストレスが軽減され、心身ともに健康な状態を維持できるようになる。また、家族や友人との関係強化にもつながり、人間関係がより豊かなものとなる。さらに、自己啓発や趣味に時間を費やすことができ、自己成長や充実感を得ることも可能となる。
企業にとっては、ワークライフバランスの推進は生産性の向上をもたらす。従業員の満足度やモチベーションが高まることで、業務への集中力が高まり、結果として企業の業績向上に貢献する。また、従業員の満足度と定着率が向上し、人材育成コストの削減や、組織の活性化につながる。創造性やイノベーションの促進、優秀な人材の確保といったメリットもある。
社会全体にとっては、ワークライフバランスの推進は、少子化対策や健康寿命の延伸、医療費の抑制といった効果をもたらす。仕事と育児の両立が容易になることで、出生率の向上が期待できる。また、人々の健康状態が改善されれば、健康寿命が延び、医療費などの社会的コストの削減にも貢献する。
これらのことから、ワークライフバランスの推進は、個人、企業、社会全体にとって非常に有益であり、より良い社会の実現に不可欠な取り組みであるといえるだろう。
2. ワークライフバランス推進の阻害要因
ワークライフバランスの推進には多くのメリットがある一方で、企業、従業員・管理職、社会構造・制度の各側面において課題やリスクが存在し、それが推進を阻害する要因となっている。
(1) 企業
企業側の課題としては、コスト増大、導入初期の業務調整の困難さ等が挙げられる。育児休業中の代替要員確保やテレワーク導入による設備投資等のコスト増加は中小企業にとっては大きな負担となることが懸念される。また、職場以外からのインターネット接続による情報漏えいのリスクなど新たな対応が求められる。
(2) 従業員・管理職
従業員・管理職側の課題は、ワークライフバランスに対する認識のずれ、個々の状況への配慮不足、そして休暇取得への罪悪感が挙げられる。また、働き方改革関連法の施行により、2019年4月から年5日の年次有給休暇取得が義務付けられたことにより、年次有給休暇取得率は向上傾向にあるものの、依然として低い水準にとどまっており 2)、企業規模が大きいほど有給休暇取得率が高い傾向にあり、従業員数の限られる中小企業では業務量の多さや属人化した業務、体制整備不足などの理由から特に休暇取得が困難な状況にある。また、個々の勤務体系に応じた賃金や待遇の見直しを図る必要があるが、そこに従業員間での不公平感が生じないよう留意する必要がある。
(3) 社会構造・制度
社会構造・制度側の課題としては、長時間労働を是とする風潮が根強く残っていることや、慢性的な人手不足が挙げられる。また、育児や介護休暇を取得する従業員のキャリアサポートが不十分な場合、職場復帰への不安やキャリア形成への影響が生じ、あえて休暇を取得しない悪循環に陥る可能性もある。
これらの課題・リスクに対し、企業は業務効率化や従業員の意識改革、柔軟な制度運用に取り組む必要があると考える。政府も育児・介護支援制度の充実、同一労働同一賃金への対応、テレワーク導入促進など、様々な政策で支援する必要がある。・・・
ここまでお読みいただきありがとうございます。
以下のボタンをクリックしていただくとPDFにて全文をお読みいただけます(無料の会員登録が必要です)。
会員登録してPDFで全て読む

ご登録済みの方は
58763文字