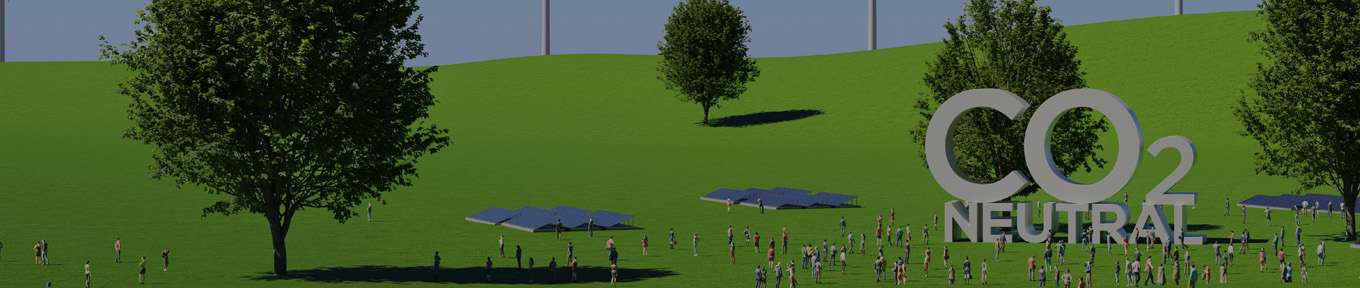
企業の脱炭素・カーボンニュートラル 一見“地味”でも、効果は地球規模?
2025.11.7
みなさんは「脱炭素」「カーボンニュートラル」という言葉に対して、どんな印象をお持ちでしょうか?
2000年前後から日本でも本格的な取組が始まったこれらの活動は、当初、一部の企業の間では「やらされ感」があったようです。ただ、こうしたイメージは近年になって大きく変わってきています。
「脱炭素」や「カーボンニュートラル」をめぐる、最新の動向や企業にとってのメリットなどについてご紹介します。
流れ
- 当初は「やらされ感」のあった脱炭素・カーボンニュートラルの取組
- 脱炭素・カーボンニュートラルの手法は?
- サステナブル経営が企業の持続的な成長に
- 脱炭素が企業価値向上にも
当初は「やらされ感」のあった脱炭素・カーボンニュートラルの取組
「京都議定書」という言葉を覚えていたり、聞いたことがあったりする人もいらっしゃるかもしれません。「京都議定書」は、1997年に京都で開催された地球温暖化防止京都会議(COP3)で採択された、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスに関し、先進国の排出削減について数値目標などを定めた文書です。
この頃から、企業に対して温室効果ガス削減に向けた取組が求められるようになり、当初は「やらされ感」で取り組む企業も多かったようです。
脱炭素・カーボンニュートラルの手法は?
近年は、当初の「やらされ感」が薄れ、より前向きに取り組む企業が増えています。
そして、企業の脱炭素・カーボンニュートラルの取組手法は多岐にわたっています。省エネ設備の導入、再生可能エネルギーの自家発電、デジタル化による業務効率化など。これはすべて、温室効果ガスの削減につながります。

実は、脱炭素を進める過程で無駄な工程や資材の削減にもつながり、企業の生産性向上にも寄与しています。
サステナブル経営が企業の持続的な成長に
サプライチェーン全体での排出量の見える化や、環境負荷の少ない製品・サービスを優先的に調達する取組も注目されています。
投資家や消費者の目も厳しくなる中、“サステナブル経営”は、企業の持続的な成長に不可欠な要素となりつつあります。
温室効果ガス削減の取組としては前述の他にもLEDの導入、空調の温度調整、電気設備の運用見直し、オフィスのペーパレス化などがあり、1つ1つは一見“地味”に見えるかもしれません。
しかし、時代の先を見据え、できることから着実に進めていくことこそが企業を存続・成長させるために不可欠な要素になっていくと考えられます。
脱炭素が企業価値向上にも
さらに企業の中には、社員からアイデアを募る社内コンペや、排出量の“見える化”で、脱炭素の取組を加速させるところも増えてきています。
こうした取組は、コスト削減につながるだけでなく、企業価値・ブランド力の向上にもつながります。つまり、脱炭素は、企業の成長と環境負荷の低減が対立することなく、ウィンウィンの関係になれるものです。
小さな工夫が大きな変化につながる。そんな感覚で、脱炭素・カーボンニュートラルの取組を始めてみてはいかがでしょうか。
脱炭素は、今や企業にとって
避けては通れない課題です。
当社では、企業の皆さまのニーズに合わせて
さまざまなサービスをご提供しています。
お気軽にご相談ください。


